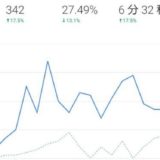ヒョングは流れる景色を静かに眺めている。大阪の天王寺駅を出発した快速電車は一路和歌山に向かって走る。ラッシュ時間が過ぎた車内には空席が目立つ。隣から若い母親と幼い娘の何気ない会話が聞こえてくる。
「お母ちゃん、お腹すいたわ」「家に着くまでガマンしーや。ご飯作ったるさかいにな」(“さかいにな”…か。関西だなぁ)今さらながら、ヒョングは自分が地方に来たのだと実感した。

彼の名はリ・ヒョング。東京朝高出身である。この春、朝大文学部を卒業し赴任先である和歌山の学校に向かっていた。車窓の外を見つめるヒョングの顔は心なしか暗かった。親元を離れて見知らぬ土地で過ごすことへの不安が彼の表情を曇らせていた。やはり生まれ育った土地を離れるのは寂しい。特に両親と離れることが一番つらかった。
一昨日の夜、ヒョングはオモニとたわいない会話を交わした。明日には旅立つ息子を前にオモニがポツリとつぶやいた。「昔、うちは本当に貧乏でね。お釜と鍋ぐらいしか家になかったんだよ。そんな時にお前が産まれたんだ… 苦しかったけどお前の笑顔に癒されて頑張れたの。大学を卒業してやっと家に戻ってくると思ったのに…」
オモニは涙ぐんでいた。ヒョングは胸の詰まりを隠すようにわざと明るい声で言った。「やめなよ、オモニ。湿った話は苦手だよ。心配しなくてもすぐに戻って来るからさ」この時は、本当に2~3年で戻れると思っていた。
「オモニ、肩をもんであげるね」そう言ってヒョングはオモニの後ろに回った。久しぶりに見るオモニの背中。オモニはその背中で俺たち3兄弟を育て、人生を背負ってきたのである。(あれ? オモニの背中ってこんなに小さかったっけ?)丸まって小さく縮んだオモニの背中を見てヒョングは切なくなった。
(オモニ、2~3年したら必ず帰ってくるよ。そん時はたくさん親孝行するから待っててくれな)そんなヒョングの気持ちを知ってか、オモニが優しく微笑んだ。